ホンモノガタリ Vol.1 「競争から共創へ。それがHonmono。」三井所 健太郎氏
- otake Ippei
- 2021年8月30日
- 読了時間: 18分
更新日:2021年11月5日

アーティスト、職人、クリエイター、Honmonoには多様な個性が集まっている。
その一人ひとりの今の想い、これまでの軌跡、これから進む道。Honmonoメンバーが語る等身大の物語、それが「ホンモノガタリ」。
第1回は、組織の代表だからこそ見えるHonmonoの今とこれからを、三井所健太郎さんに聞いてみた。
取材日:2019年12月17日聞き手と文:大竹一平(MtipCreative㈱代表)
やっぱワクワクがないと
三井所
この前、Honmonoの2019年の総括と2020年に向けた想いを資料に纏めていて思ったんですけど、Honmonoの活動って率直に言ってしまえば、「ワクワク」の延長にあってほしいと思ったんですよね。
大竹
ワクワク?
三井所
そう、自分で考えを整理していて思いました。プロジェクト、イベント、ほんとに小さなことでもいいんですけど、やっぱり「ホンモノおもしろいわ」がないとHonmonoに人は集まらない。
人が集まらないとメンバー同士の共創は生まれないし、新たな出会いや新たな機会も生まれない。
大竹
ワクワクと言っていいと思うんだけど、実はおれとしては、これまでHonmonoの活動を仕事として取り組んだことは一度もなくて、完璧に遊びとしてやってきました(笑)
三井所
ありがとうございます(笑)
大竹
仕事にするとどうしても「うまくやらないといけない」「成功させないといけない」っていう想いが強くなるから、委縮しちゃったり、マージンとったりしちゃうんだけど、会社の外にあるHonmonoでそれをやったら加入してる意味がなくなるなと。
自分の仕事じゃ出来ないことをHonmonoで試して、刺激をもらって、自分と自分の会社の可能性を広げたい、だからHonmonoでは本気で遊ぼうと。

ミートアップでは新しいメンバーの活動を体感し楽しむことから始まる。
三井所
Honmonoが目指している部分でもあるんですけど、一人ひとりが人間性を活かしながら自主的に動いて、結果を出して行くっていうのが、これから求められる働き方になると思うんです。
仕事には「達成型」と「展開型」っていう2つがあって、軍隊式に上からの命令を受けて個人が動いて、組織の力で目標を達成するのが「達成型」、一人ひとりが競い合う競争ありきですよね。

大竹
日本が敗戦から立ち直るために、昭和を支えてつくり上げてきた価値観ですね。
三井所
その時代の背景というのはあって、高度経済成長期の日本は所得倍増計画から始まって経済発展という大きな目標、社会の流れがあったから、それに沿って企業や個人が猛烈に競い合うことで結果を出せてきたと思うんです。
大竹
でも、時代は変わってきた。
三井所
ですです。インターネットとスマートフォンが当たり前になって、時代は変わりました。
誰もがメディアとして情報を発信できるようになり、変化のスピードは上がり、価値の多様性もどんどん広がっています。
達成型で見られた「上の人が出す1つの命令」は、末端に届く前にもう社会が変化してしまっているかもしれないし、そもそも多様な価値観で広がり続ける海に、一滴の水を落としたところで、周囲に与えられる影響はどんどん小さくなっていきます。
だから今はもう、成長するための組織の形や、仕事の価値観も大きく変わっているはずです。
ティール組織といった概念も、現実的に取り入れるべき段階にきています。
※ティール組織とは?
上司部下のような概念は存在せず、組織の一人ひとりが意思決定権を持つ。組織の存在意義をベースに事業が自発的に展開される次世代の組織モデル。

大竹
そこで、Honmonoが登場するわけですね。
Honmonoは「共創」する集まり

三井所
これからの社会で求められるのはティール組織のように、個々それぞれが持つ能力や主体性をしっかり磨きながら、周囲と協調して結果を出していくことだと思います。
だからHonmonoの働き方の基盤は「展開型」。
個々が自主的にチャレンジして、その過程で起こる出会いの輪を広げて、結果的に影響力がどんどん大きくなっていくような。
“競争”ではなくて“共創”しながら成長していくための組織にしたいです。

Honmonoの全体構想
大竹
展開型の起点になるのがHonmono。
三井所さんが面白いなと思うのは、大学を出てけっこう大きな企業に入ってますよね。
達成型社会のど真ん中みたいな組織で、上から下りてくる仕事を大人しく日々こなす、ある意味そんな“楽”もできるのに。どうしてわざわざHonmonoをつくろうと思ったんですか?
三井所
就職して、Honmonoを起ち上げるまでに8年から9年、会社員に専念してたんですけど。
実はその前、会社に入る前から自分の中ではずっと、「自分で価値を生み出して、それを人に届けて喜んでもらう」っていうことに価値観やよろこびを感じていたんです。
ただ、それを形に出来る手段がない大学生活だったんです。
始まりはデザインと工学
大竹
大学ではなにを勉強してたんでしたっけ?
三井所
クリエイティブ系でした。
九州大学の芸術工学部といって、デザインもやるし工学もやるし、いろいろ全部学ぶとこなんです。
たとえば絵を描いたり粘土をこねたりする一方で、デザインアーキテクトといって、物理を学んで建物の外観だけでなく構造や設備までを含めたデザインをまとめていったり、プログラミングをやったり、CGもつくったり、とにかく芸術と工学を一通りやるんです。で、その結果なにも残らなかったみたいな(笑)

反省だらけの大学生活
大竹
いろいろやってなんでも出来るって、結局はなにも出来ないと同じことになっちゃう(笑)
三井所
そうそう(笑)
でもまさかそうなるとは思わないので、もともとはそういうことを学べば、価値を創り繋げる仕事ができるんじゃないかって。
でも突き詰めれば、具体的にこれがやりたい!っていうのがなかったんですよね、結局は。
だから学生時代の浅い知識なりに、総合通信企業に入れば、なにか自分がやりたいことを見つけられるんじゃないかと思ったんです。
大竹
たしかにいろいろやれそうな会社だし、仕事に夢だって持てそう。
三井所
それで、就職活動の時から面接で「中小企業を相手に仕事をしたい」と言い続けてたら、企業側からするとそれが珍しかったみたいで採用されて、入社後は実際に中小企業向けに営業する部署に配属されました。
大竹
中小企業?
三井所
なんとなく、「自分でなんとかできる仕事に就こう」っていうのは無意識の中であったんでしょうね。
大企業が相手だと、営業先の担当者の上司がいて、本部長がいて、役員がいて、自分の手を離れてからたくさんの決裁を受けないと話が決まらない。
でも、中小企業が相手なら自分で受注できて、自分で信頼関係を築いていけて、そんな風に仕事の中にいつも“自分”がいるからおもしろいだろうなって。その部署でずっと長く仕事が出来たんです。それがよかった。
大竹
たしかに、中小企業が相手なら場合によっては社長が直接出てくるだろうから、仕事の手応えは強く感じられるはず。でもそれを考える大学生って、なかなか面白い人だと思うんですけど。
三井所
人に縛られたくなかった(笑)
そういうのがめんどくさかったんでしょうね。
クリエイターの気持ち、サラリーマンの気持ち
大竹
でも大きな組織に入ってしまうと結果的には…。
三井所
いろいろ苦労はしました(笑)
ただ、会社にいて一番よかったことは、企業との交渉を心と頭、それに体に染み込むぐらいまでずーっとやれたことですね。
自分で言うのもなんですけど、けっこう貴重な存在だと思うんです。
クリエイティブなことや、それに携わる人たちの考え方もある程度は分かるし、がっつりビジネス界の、もっと言えば厳しい縦社会のさなかにいるサラリーマンのお客さんの気持ちも分かるとか。
大竹
うーん。ちゃんと今につながってますね。
三井所
つながってますね。
大竹
その中で、アカパン(A.Ka Project)とはどうつながるんだろう?
三井所
大学を出て始めて東京に来て、営業マンとして配属されたからには「会社で1位になってやる」っていう気持ちが強かったんです。
でも、実際にはぜんぜん結果が出なくて。
負けず嫌いで、仕事でもすごく他人と自分を比較する性格だったし、九州から東京に出てきて「東京、大阪の学生には絶対負けねえ」とか、世間のサラリーマンに対する偏見とかいろいろ重なって、結果的にはとにかく自分の弱さを隠したくて、当時は身の丈以上に、弱い犬みたいに吠えてました…。
大竹
20代ってやっぱそうやって意味なく尖るものなんだ(笑)
三井所
「やっぱりダメだった」って泣き言を言うのはイヤだし、逃げ場がないし数字は上がらないしで、しんどくて辛くてクタクタになってる時間がしばらく続きました。
そんな感じで1年ぐらい過ごしてたある日、巣鴨の地蔵通りのお店でアカパンを買って履いたら、次の日に大口の受注が取れたんですよ。
大竹
すごい出会い(笑)
三井所
すごい出会いですよね(笑)
もともと赤が好きだったんで、1,200円ぐらいのアカパンを買ったら、大口受注が取れたんですから。それでもう完全に脳が「赤=うまくいく、やる気出る」みたいになって、それからは週に2回か3回は勝負のアカパンを履くようにしてたんです。
もちろん営業成績とアカパンはなにも関係ないでしょうし、それまでの積み重ねとか時期的なものがあったんでしょうけど、それからなんか少しずつ自信を持てるようになったんです。
うまく循環して営業の数字も2年目、3年目でどんどん上がるようになってきて。
Honmonoを生んだ感情の“根っこ”
大竹
人の気持ちって不思議だよね。なにか小さなきっかけでどんどん変わっていく。
三井所
おもしろいですよね。それで「これはアカパンだ」っていうことになって、もっと多くの人にその力を知ってもらおうとアカパンをつくるようになって、それがあったからHonmonoをつくることができて…。

地球最高峰の原料と日本最高峰の技術で作ったアカパン。
大竹
そうつながってくるわけだ。アカパンを始めたのはいつ頃?
三井所
会社を休職してからだから、2018年です。
……あのぉ、ですね。魅力的なアーティスト、職人、クリエイターをつなげたいということ、自分が感じたHonmonoをつくった意義とか、必要性とか社会的背景とか、そういうことに1つもウソはなくてどれも絶対にあるし、本当に言ってる通りに思ってます。
ただ、Honmonoをつくった時、自分の中のもっと深いところにあった根っこは、実は1人でアカパンの事業をやってて寂しかったんだと思うんですよね。
1人で仕事をするって自由だとか、1人になったんで昼間からジム行ったり、酒飲んだりとか、みんなが働いてる時にやる優越感があるかなとか思ったんですけど、いざやってみたら超さみしい、みたいな。
「孤立」という思いがある一方で、でもアカパンのおかげで仕事上のつながりは広がっていたので、そこのチームはつくれるな、ていうか仲間が欲しいな、とか。

アカパンを通して伝説の和太鼓集団「鬼太鼓座」とも繋がることができた
しかも考えてみたら、そんなつながりがどんどんどんどん展開していったら、きっとおもしろいなとか。Honmonoをつくった根っこには、そんな想いもあった気がします。
大竹
アカパンをやることで、1人でゼロから新しい世界をつくる寂しさと楽しさを知っちゃったんだ。
三井所
そうですね。だからHonmonoはウソ偽りなく、ちゃんと語れる場にしようと。
一歩踏み出し、大切な人たちに出会う
大竹
とはいえ、アカパンにしてもHonmonoにしても、「やれたらいいな」とは思っても、実際に自分で動く人って、あまりいないと思う。
三井所
最初、Honmonoをつくろうと相談した伊藤ミナ子さん(漆芸作家)にも言われたんです。
アーティストとか職人とか、異業種をつないでいくことって、始めてみても半年ぐらいするとモチベーションが下がってやめていくケースをわりと見てきたって。
でも、なんでしょうね。
自分には確信というか自信があったんです。
それは身をもって企業組織の世界と個のクリエイティブの世界を体験してきたから。
この2つの世界にあるギャップと、そのギャップを埋めたときの化学反応は必ずある。
自分がやりたいことだし、やるべきことだと。
しかも、今でも当時の気持ちが変わらず続いているんですよね。
大竹
うーん。それでもうそろそろ1年経つわけか。
Honmonoをつくる前に準備期間ってあったんですか?
三井所
3か月ぐらいですかね。
いずれにしても1人ではできないと思ってたところに、佐久間一璃さん(Videographer)に出会ったのが大きかった。
インスタグラムのアカパンのPVを見た佐久間さんが「かっこいいですね」とメッセージをくれて、私も佐久間さんのPVを見てかっこいいと思って、「会いましょう」と。
ちょうど佐久間さんも会社を辞めて1人で仕事を始めたタイミングで、お互いに「楽しいことをやりたい」ってことでシンパシーがあったんでしょうね。だからHonmonoの構想の段階から相談していました。

佐久間さんとの出会い
大竹
Honmonoが始まった瞬間。
三井所
最初に思ったのが、人と人とがつながってコミュニティをつくるだけだったら、たぶん維持するのは難しいだろうなと。
学生とは違うのでメンバーとして会員が集まってもその人たちはなかなか会う機会がないだろうし、なにか理解しあえてつながれる核がほしい。その“なにか”を表現するものがあるとしたら、映像だろうなと。
そう思ってた時に、佐久間さんが「映像をつくる部分はおれがやるから、人とのつながりはよろしく」って。
そこから始まりました。で、「誰撮る?」「じゃあ、伊藤ミナ子さんで」みたいな。
大竹
ミナ子さんが3人目のHonmonoだ。
三井所
そのきっかけもインスタです。
インスタって、その人の世界観がすごく分かるじゃないですか。
その時すでに自分の脳の中では本物、スペシャリストを集めたいという想いはずっとあって、そういう目でインスタを見てたんです。
その時にミナ子さんの作品を見た時に、「この人エッジ効いてるな」と思って、すぐ連絡をとったみたいな。
佐久間さん、ミナ子さん、私、この3人で最初の流れをつくったような感じです。
大竹
スタートで、いい2人に出会えた。
三井所
ほんとにそう思います。
ゼロからイチにする時に佐久間さんがいてくれて、その流れに知見と裏付けをつけてもらえたのがミナ子さんな気がしています。
大竹
ゼロからイチにして、さらに流れをつくるのには想いとパワーがいるから。

奮闘しながらも初めてのメディア取材を受けたときの3人
負荷、反省、教訓
三井所
そうですね。実は立ち上げの時に自分自身で反省していることがあって。
大竹
反省?
三井所
はい。
三井所
立ち上げの時、とあるメンバーに対してその想いとパワーをかけすぎてしまったんです。
Honmonoの創生期、まだガリガリだった時期を乗り越えるには、どうしても無理をするパワーが必要でした。
その分あるメンバーに、同じ目線で、感覚も同じで、優秀な人だったからこそ、期待しすぎてしまい、めちゃくちゃ負荷をかけてしまっていたんです。
Honmonoを始めて一番に悩んで反省したのはそこです。
Honmonoはみんながスペシャリストだし、みんなでつくり上げていくものなのに、1人に過度な負荷とプレッシャーを与えてしまいました。
大竹
起ち上げだし、頼らざるを得なかった。
三井所
頼らざるを得なかった。
もちろん、初期の頃はその人もまだ状況的に追い込まれてなかった。
だから本当に楽しくやってくれていたんですけど、ある時点、途中から変わった時があったんです。
それは自分も見ていて気付いてはいたんです。
「あっ」という時が。
なんか表情に余裕がないなとか、酒を飲みに誘っても行けなかったりとか、でもその人はめちゃめちゃ優しい人なので、自分からは口にしないんですよね。
でも聞いたら「Honmonoにリソースかけたいけど、なかなか…」と、でもそう聞いても私は「いやいや、Honmonoはこれからイケるから。大丈夫だから」って。
そう言われてその人自身も自分でHonmonoを後押ししてしまった手前、引き返せなくって……。
追い込んでしまった。
大竹
非営利な一般社団法人っていう組織で、まあ会社でも同じだろうけど、そういうこともあるんだろうなあ。
三井所
経営者とか岩本涼君(メンバー、TeaRoom代表)からも聞いていたんですけど、スタートアップで「ここから勝負!」っていう時に右腕が離れるってのは、けっこう言われてきてたんですよ。
自分にはそんなことないだろうと思ってたんですけど、実際にはまさにその状況で。
でもそれはステージが1つ上がった時だと感じたというか。
たぶん「属人的な組織運営はこれから通用しないよ」って、経営の神様が言ってくれてるんだなと。だからチームでやりなさいと。チームでやらないと組織が成り立たないよと。
大竹
うんうん。
三井所
その後は奔走しながらもなんとかチーム体制を作りました。
この反省の過程、その人と交わしたやりとりは、必要なステージだったのかなと思ってます。
もし属人的な体制で、無理やり続けていたら、Honmonoもそのメンバーもずっと不幸のままでした。
だからこそ今は、その人が自身の挑戦を終えたときに、気持ちよく戻ってこれるようにチーム体制を整えておくことが私のやるべきことだと思っています。
大竹
誰かに頼らざるを得ないけど、結果それでお互いしんどくなるっていう時はあるよね。
楽しんでやれてる間はきっといいんだけど。
誰にでもHonmonoの活動に対する気持ちの波とか、現実的にかけられる時間の問題はあると思うから、誰かがやれない時に、他の誰かがフォローするような組織であってほしいかな。
それで、その人が帰ってきた時に、迎えてくれる組織であってほしい。
三井所
そうそう。そうなんですよ。
同じメンバーが固定的に動いてる組織って凝り固まると思うし、「1年前によく来てたあの人が、また来てくれてる」とか、メンバーが流動的に入れ替わったりしながら、常にどんどん動いている組織にしたいです。

出てきた!
大竹
そういう意味では、代表としてやってきたここまでの手応えみたいなものはありますか?
三井所
嬉しいなと思うのは、メンバーがそれぞれ、西端実歩さん(映像ディレクター)の映像、やじーさん(矢嶋巧、SNSディレクター)のSNS、犬塚崇文さん(金胎陶芸家)のhitotoiコラボ、このホンモノガタリもそうだし、プロジェクトがどんどん出てきてますよね。
これまでは私がなんとなく種をまいて、みんなで育てていくみたいな形でしたけど、それが今は変わってきて、私がなにも言わなくても始まってる。
「やっと出てきたな」って思ってます。
大竹
動き始めてる感じは、ある。
三井所
はい、そしてもう1つ。
Honmonoの本拠地「COHSA SHIBUYA」と提携出来たことが大きな前進となりました。
大竹
確かに。メンバーから見てもとても魅力的なパートナーシップです。
三井所
Honmonoは素晴らしいメンバーとプロジェクトは生まれていましたが、「場所」がなかったんですね。
レンタルスペースなどを打ち合わせ毎に借りていたのですが、それだとなかなか気軽にメンバーが会えないし、イベントをするにしてもどうしても「Honmonoの匂い」が出ない。
大竹
SHIBUYA COHSAがあれば、作業も打ち合わせも、ワークショップやイベントも全て出来るもんね。まさにホームといった感じ。
COHSA SHIBUYAがいつでも利用可能に。
三井所
はい。
そしてCOHSA SHIBUYAを運営する株式会社山崎文栄堂の山崎社長、若狭専務との出会いも衝撃的でした。
Honmonoと同じ想いと志を持たれていたこと、尊敬する経営者でありながら、同志としてHonmonoをサポートしてくれていること、とても心強いです。
大竹
心強いメンバーと環境が増えましたよね。
三井所
本当にご縁に感謝です。
もちろん、まだやらないといけないことはたくさんあると思いますけど、メンバーそれぞれの意思を持ったプロジェクトがどんどん出てきてるし、Honmonoを応援するパートナーも出てきた。
手応えはあるなと思います。
プロジェクトを積み重ねることで外部にも内部にもお互いの信頼関係ができてくると思うし。

Honmono協会のクリエイティブ担当西端さん(中央)と山崎文栄堂の山崎社長(右)
心強いパートナー
大竹
そこは地道にやっていくしかないよね。
三井所
地道にやっていくしかないですね。
地道にやって、内部にも外部にもファンを増やしていく。
これからやらないといけないことは、今はHonmonoの内部にメンバーがいてくれて、外にはHonmonoになりたい人、入りたい人、その人を応援してくれる人たちもいる、だからもう1つ、Honmono自体のファンになってくれる人、それをつくることです。
「Honmonoに入るわけじゃないんだけど、Honmonoってなんかいいよね」みたいに思ってくれる人を増やしたい。
これからのHonmono、2020へのHonmono
大竹
そういう意味では、これからHonmonoっていう組織はどうやって運営されていくんだろう。
メンバーの会費と企業からの協賛? それともHonmonoならではのアーティストの作品とか、クリエイターが生み出す事業で運営資金を得ていくイメージ?
三井所
メインは事業収益で運営していきたいですね。
既に映像制作は引き合いが多いし、たとえばライティングはまだ内部事業だけどこれから外部事業になって、SNSもマンガも同じようになっていく。
WEB、SEO、デザイン、ブランドコンサルなど一流のメンバーがHonmonoに在籍しているので、外部からHonmonoで請ける時はメンバーそれぞれの収入にもなる。
企業に対しても個人に対しても、ギブ&テイクの関係でお互いに価値や成果を築く。そういうwin-winの形になるのが一番かなと思ってます。
大竹
なるほど。
そういった展開を続けるにあたって、どんなメンバーにHonmonoに加わって欲しい、ってのはある?
三井所
そうですね。
まず、Honmonは「ホンモノを目指す人」が集まるチームです。
今活躍している、有名だ、フォロワーがこんだけいる、こんな肩書きだ、こんなに会社がデカイんだ。というのは一切関係ありませんし、上下の優劣もありません。
大竹
確かに。偉い人でもエラそうにしている人、一人もいないよね。
三井所
はい。
逆に言えば、誰も上から指示しないし、下に指示することも出来ないということです。
自身が主体的に動き、仲間と協力してチャレンジした人のみが、新たな機会やパートナーを得ることができますし、そういった人が共感を得て、影響力を広げ、成長をしていきます。
大竹
地道な信頼の積み重ねがとても大事。
三井所
そうなんです。それさえ守られていれば、
「メンバーとコラボレーションして自身の事業を多くの人に知ってもらいたい」とか、
「信頼できるクリエイティブメンバーを仲間にして、事業の価値をもっと上げたい」とか、
「自社の若手に、会社に縛られず0から事業を生み出す経験をさせたい。」など、
法人、個人問わずHonmonoの活用法は無限大です。
ぜひ、扉を叩いて欲しいと思います。
大竹
確かに自分次第でなんでもチャレンジできるのがHonmonoの魅力ですね。
そんな中で、三井所さん自身が今一番やりたいことはなんだろう?
三井所
そうですね、、「祭」をしたいですね。
お祭りってやる側も参加する側も楽しんでる「ワクワク」の究極のコンテンツじゃないですか。
そのレベルまで仕上げていくっていうのは、目標としてあります。
大竹
うん、それおもしろい。この1年で出来るかな?
三井所
2020年、節目の年だし、日本はオリンピックもあってお祭りイヤーです。
1年前にはここまで出来ると思ってなかったので、いい形で来てると思うんです。
さっき言ったHonmono自体のファンになってくれる人をつくって、Honmonoの人と活動をどんどん出して行って、やる側と参加する側の共創文化の輪を広げれば必ず出来ると信じてます。
ワクワクとチャレンジをもってHonmonoの輪を広げながら。祭り、やりたいですね。

初心を忘れず、変化を恐れず、2020年の Homonoも展開し続けます。
<おわり>

%20(7).png)




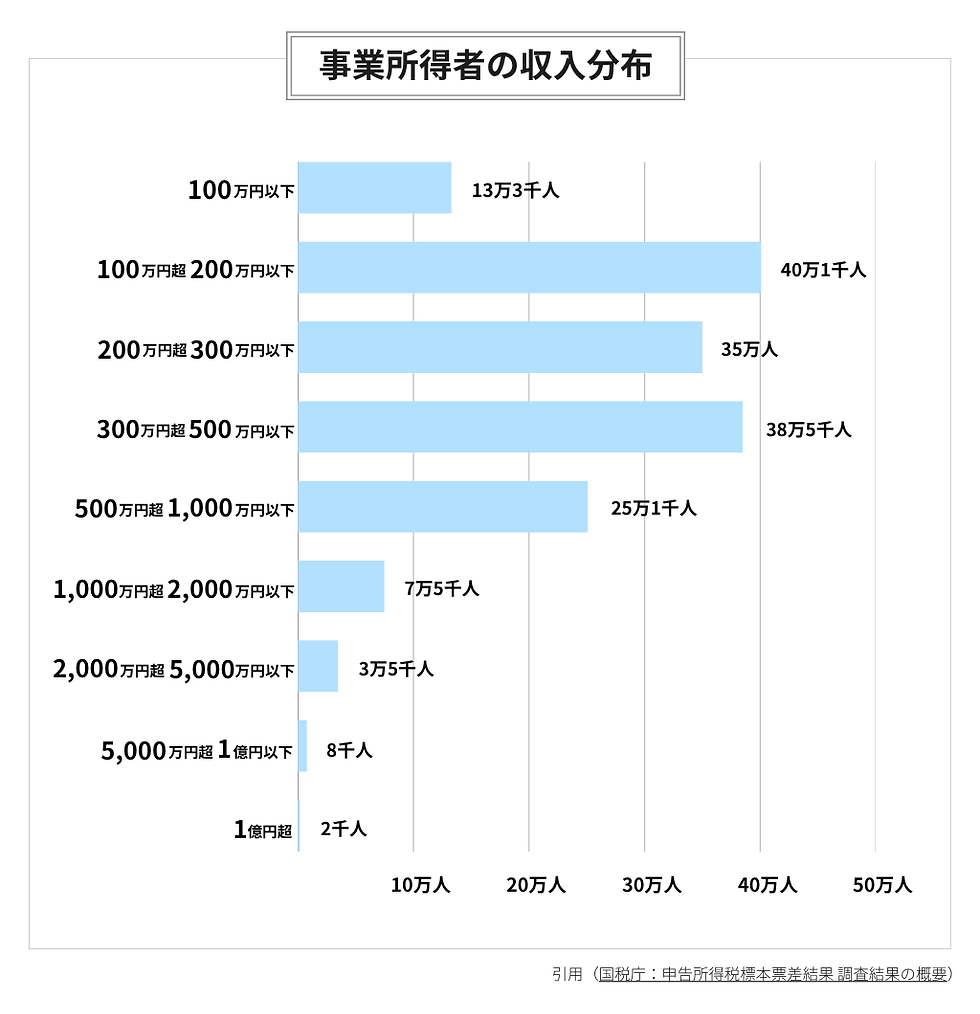

コメント